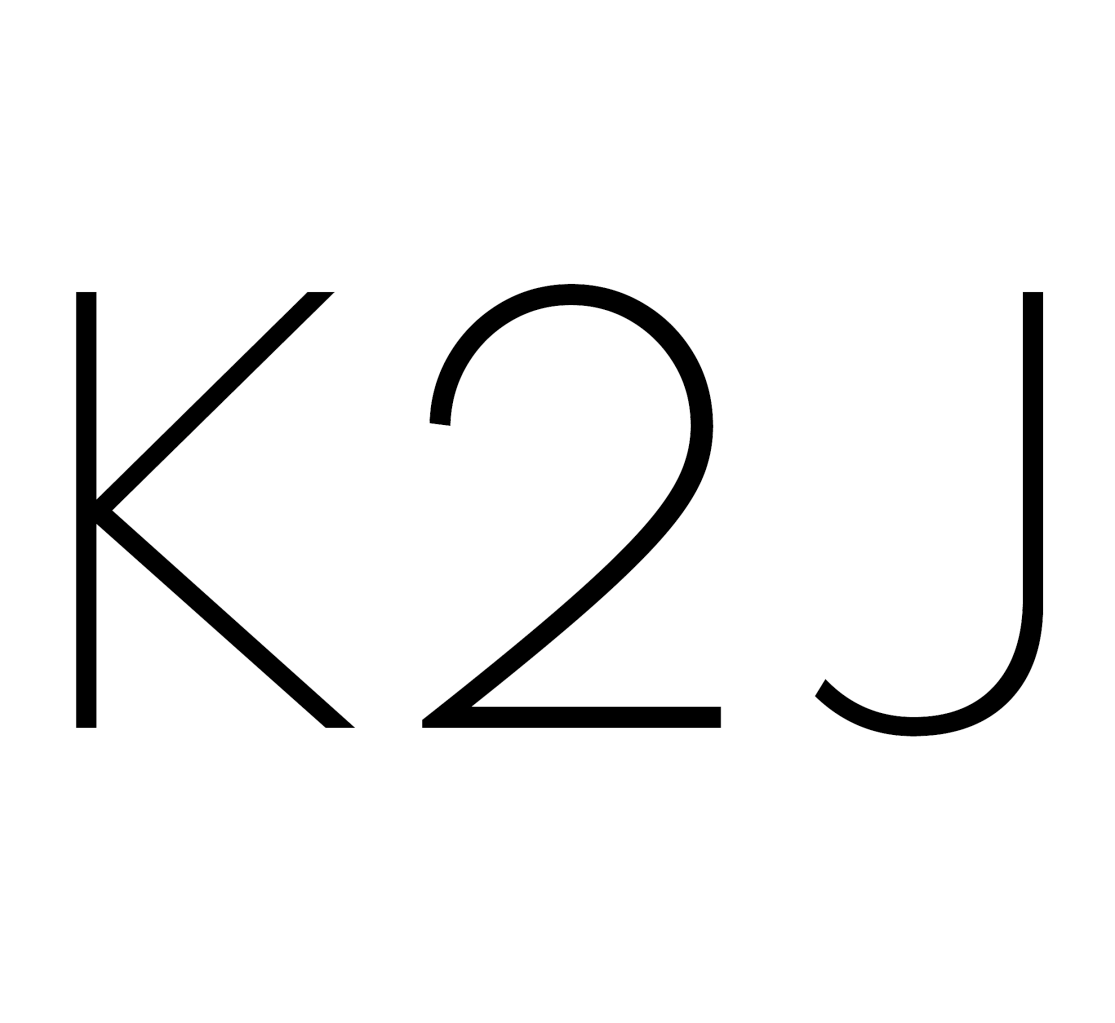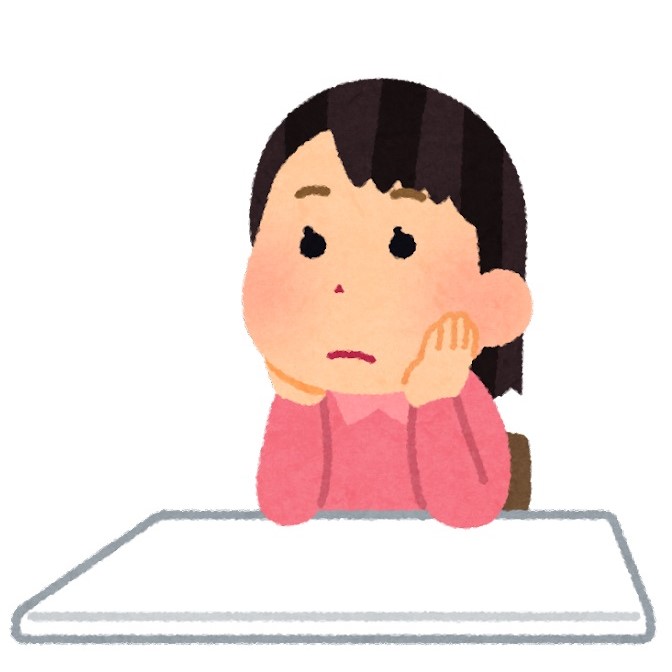
こんな疑問をお持ちの方へ。
ある日はブルベ夏と言われたのに、別の日はイエベ春。ネットで自己診断してみたら、また全然違うタイプが出てきて、何を信じればいいのかわからなくなる。こんな経験をしている人は少なくありません。
ネットで検索すると、「パーソナルカラー 意味ない」「毎回違う」というワードをよく見かけます。でも実は、診断がブレるのにはちゃんとした理由があるんです。正しく活用すれば、意味がないどころか、「色選びの迷いを減らすツール」に変わります。
本記事では、結果が毎回違う4つの原因をプロの視点でわかりやすく解説しながら、診断をどう受け止めて活かせばいいのかを徹底的にお伝えします。さらに「似合わない色を着たい時の対処法」など、実生活ですぐ役立つテクニックも盛り込みました。
読み終える頃には、「診断に振り回される側」から「診断を使いこなす側」に変わっているはずです。今日からの服選びやメイクが、ぐっとラクに、そして楽しくなるはずです。
それでは早速見ていきましょう。
【結論】「パーソナルカラー診断は意味ない」は半分正解。正しく使えば武器になる

パーソナルカラー診断は「意味がない」と言われることもあります。これ、実は半分は正解なんです。なぜなら診断結果は、環境や条件によって変わりやすいから。
たとえば、照明の色温度が少し違うだけで、肌映りが青白く見えたり黄味を帯びて見えたりするんです。とくに、オンライン診断の場合はこの影響が出やすいので、結果がまったく違うこともあります。
たとえば、僕は普段「イエベ秋」っぽいと言われるのに、オンライン診断だと「イエベ春」だったり、急に「ブルベ」という診断になったりします。
結果が毎回違うと、意味がないと思うのも当然ですよね。
さらに、「診断結果に納得できない…」という感情も、診断そのものを活かせない原因になりますよね。自分の理想や感性と結果が噛み合わず、なんとなく「これでいいや」となり、結局好きな色を選んでしまうパターン。でも、それでは診断を武器にできていません。
じゃあどうすればいいか?答えはシンプル。信頼できる専門家のもとで、納得感ある診断を受けること。
パーソナルカラーリストの資格を保有する熟練の診断士さん、照明やドレープの管理が行き届いた環境、客観的で納得できる説明があると、あなたの色選びをサポートする武器になります。
パーソナルカラー診断の基礎|イエベ / ブルベの本質を理解しよう
実際にパーソナルカラー診断を受けると「なんとなく分かったけど、これって本当に正しいの?」と疑問を感じる人も多いはず。
まずは、パーソナルカラー診断の基礎と、イエベ・ブルベの考え方、そしてその限界を整理していきましょう。
パーソナルカラー診断とは?
パーソナルカラー診断は、その人の肌と調和しやすい色(=似合う色)を見つけるための方法。基本は資格を持った専門家が、100色前後のドレープ(色布)を首下に当て、顔色の見え方を比較しながら色を絞り込んでいくという流れです。
- 顔色がよく見えるか
- 肌色がクリアに見えるか(透明感が出るか)
こうした視覚的な変化をもとに「似合う色の方向性」を判断していくわけです。
イエベ / ブルベを決める「アンダートーン」とは?
パーソナルカラー診断の根幹になる考え方が「アンダートーン」。アンダートーンとは、肌に含まれるベースカラーの傾向を指します。
- イエローベース(イエベ) → 肌のベースが黄み寄り。温かみのある色が調和しやすい
- ブルーベース(ブルベ) → 肌のベースが青み寄り。涼しげな色が調和しやすい
化粧品業界では、イエベ=オークル系、ブルベ=ピンク系として色展開されることもあります。
「イエベだから赤は似合う」は誤解?
ここまで話を聞くと、
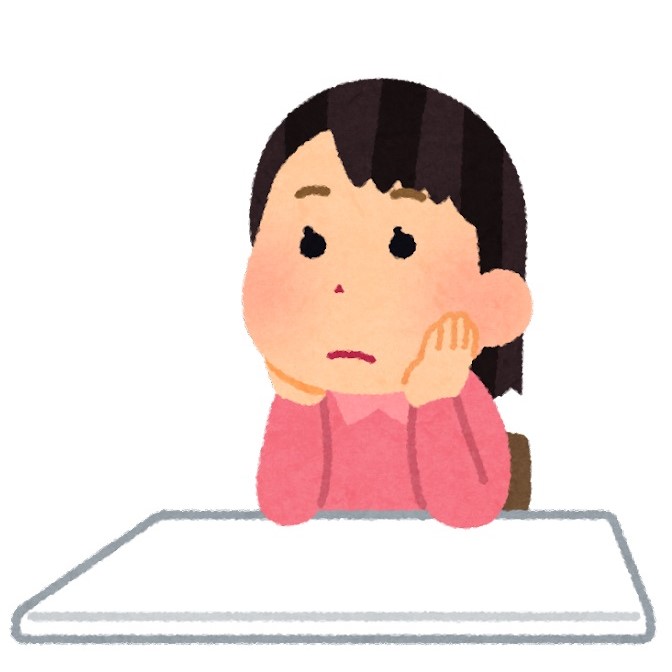
と考えてしまう人が多いはず。でもこれは大きな誤解です。
「赤」といっても、オレンジに近い朱赤から、紫寄りのワインレッドまで幅広いです。前者はイエベ向き、後者はブルベ向き。同じ赤でも、似合うタイプは全然違います。
逆に「青は似合わない」と思われがちなイエベでも、ターコイズやティールブルーのように黄みを含んだ青はしっかり調和します。
つまり、「イエベ=赤」「ブルベ=青」みたいな単純な構図ではなく、色相の微妙な黄み・青みの差こそがポイントなんです。
4シーズン分類|スプリング・サマー・オータム・ウィンター
イエベ・ブルベの2分類だけでは情報が粗すぎるため、さらに細かく分けたのが「4シーズン分類」です。それぞれの季節イメージは、アンダートーンと色の明暗・鮮やかさによって決まります。
- スプリング(春):イエベ × 明るく鮮やか
- オータム(秋):イエベ × 深み・くすみ
- ウィンター(冬):ブルベ × 明るく鮮やか
- サマー(夏):ブルベ × 深み・くすみ
イエベ・ブルベの「2軸」からさらに「明度・彩度」の要素を加えることで、より精度の高い提案が可能になるわけです。
これがパーソナルカラー診断の基本ですが、「なぜ結果が毎回違うのか?」という疑問が残りますよね?次の項で理由を解説します。
パーソナルカラー診断の結果が毎回違う4つの理由
パーソナルカラー診断の結果が毎回違うのはよくあることです。これには4つの理由があります。
① 照明・環境(自然光/色温度/背景色)
診断の精度を左右する一番の要因が「光」です。照明には「色温度」という概念があり、光の種類で肌の映り方が大きく変わります。
- 青白い蛍光灯 → 血色が悪く見えて、ブルーベース寄りに見えやすい
- 電球色の温かい光 → 黄みが強調され、イエローベース寄りに見えやすい
- 自然光 → 午前と午後で色温度が変わるため、時間帯でも印象が変化する
さらに壁やカーテンの色が反射して、肌にわずかな色かぶりが生じることもあります。
つまり、同じ人でも環境によって違う答えが出てしまうのは当然なんです。
色彩学では「北窓昼光(晴天時の日の出3時間後~日の入り3時間前までの、北窓から入る安定した自然光)」が、最も正確に色を判断できる環境だとされています。人工照明なら5,000K前後の白色光が理想に近いといわれています。
② 診断方式の違い(対面/オンライン/自己診断)

診断のスタイルも、結果を大きく左右します。本来の診断では対面式で、100色以上のドレープ(色布)を首下に当てて顔色の変化を比較しながら、少しずつ絞り込むのが基本です。
- オンライン診断 → カメラや画質、フィルター、光環境の影響を受けやすい
- 自己診断 → 手軽だけど客観性に欠け、思い込みに引っ張られやすい
オンラインやアプリは便利ですが、まだまだ「補助的ツール」にとどまるのが現実です。
③ 当日の条件(年齢・日焼け・体調)
人の外見は固定ではなく、日々変化します。
- 年齢によって肌の明度や質感は変わる
- 夏の日焼けや冬の乾燥で肌トーンが上下する
- 髪を染めると全体のコントラストが変わる
- 体調不良の日は血色が失われ、肌の色がくすんで見える
こうした要素がその日の診断結果に直結するので、「先月と今月で違う」というのもあるあるなんです。
④ 診断士の熟練度と主観バイアス
最後に大きいのが、診断士自身の経験値。
パーソナルカラー診断は、最終的には人間の目による観察に頼っています。なので、100%の精度は出せないという限界があります。熟練した診断士ならまだしも、経験が浅いと「先入観」が入ることもあり得ます。
さらに、「似合う」「似合わない」の判断には主観がどうしても混じるので、診断士の数だけ微妙に違う答えが存在しても不思議ではありません。
パーソナルカラー診断の正しい活用方法
診断の本質は「決めつけ」ではなく「傾向を知る」こと
パーソナルカラー診断を受けた人がやりがちなのが、「似合う色=選ばなきゃいけない色」「似合わない色=一生NG」と決めつけてしまうこと。これも大きな誤解です。
パーソナルカラーは、似合う色を決めつけるものではありません。本質は「どんな色が調和しやすいか」という傾向を教えてくれるコンパスのような存在です。なので、実際は選択肢を減らす必要なんてまったくありません。
たとえるなら学校の勉強。診断で「似合う」とされた色は、あなたの得意科目。「似合わない」とされた色は、あなたの苦手科目。苦手でも、勉強方法を工夫すれば克服できるのと同じで、似合わない色も小物や配色の工夫で素敵に着こなせます。
ファッションは自由。ルールはない
そのうえで、パーソナルカラーは「おしゃれに見えやすいセオリー」を教えてくれる参考書のような存在です。「私はイエベだから○○は絶対に着られない」と思い込んでしまうと、逆にファッションの幅を狭めてしまいます。
本来の目的は、「似合う色の傾向」を知って、ファッションを自由に楽しむこと。着たい色があるのに「診断に反するから着られない」と感じてしまったら、それは本末転倒です。
大切なのは、「似合う色」をベースにして日常の軸を作る、「似合わない色」は工夫次第で楽しむ。このバランスをとることなんです。
結局のところ、診断結果をどう受け止めるかで、それが「意味がないもの」になるか「大きな武器」になるかが決まります。
では、「似合わないと診断された色」を実際にどう使えばいいのか?次の章では、具体的な取り入れ方を詳しく解説していきます。
パーソナルカラー診断で「似合わない色」を着たい時のプロテクニック
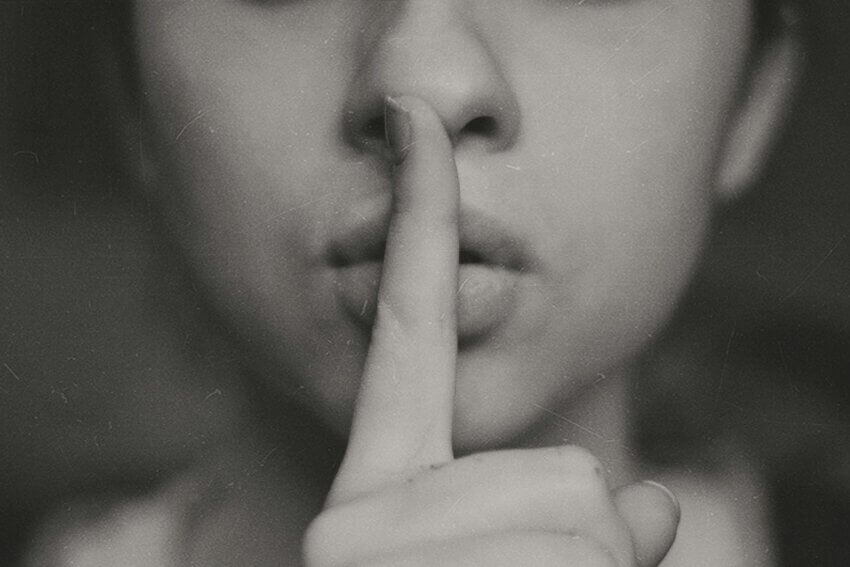
① 顔まわりは避けて、ボトムスで取り入れる
似合わない色の一番の落とし穴は「顔色が悪く見える」こと。つまり、顔まわりさえ避ければ影響はグッと減ります。
苦手な色のトップスは避けて、スカートやパンツなどのボトムスで使うのがポイント。靴・バッグで取り入れると、顔から離れるので悪影響が出にくいです。
たとえば「ブルベ冬」と診断された人が「オレンジ」を着たいなら、顔に近いニットではなく、ボトムスや小物でオレンジを取り入れるとぐっと自然になります。
② 配色比率を工夫して、小さな面積でアクセントにする
もうひとつのコツは「配色比率」。苦手色は面積を小さくすると、影響が出にくいです。具体的には、バッグ・靴・ベルト・アクセサリーで差し色として投入するのがポイント。
羽織りやジャケットの下に、チラ見えするインナーとして忍ばせるのもアリです。
自分でできる簡単なアンダートーン診断方法
プロにパーソナルカラー診断してもらうには時間もお金もかかりますよね。そこで、まずは自宅でできる「超シンプルなアンダートーン診断」を試してみましょう。
精度はサロンほど高くはありませんが、自分の肌がイエローアンダートーン(イエベ)寄りか、ブルーアンダートーン(ブルベ)寄りかをつかむには十分です。
① ベージュ vs グレー
- ベージュが似合う → イエベ
- グレーが似合う → ブルべ
これは定番チェックのひとつ。ベージュは黄みを含み、グレーは無彩色なので、肌のベースカラーを浮き彫りにしやすいんです。
② 茶色 vs 紺色
- 茶色が似合う → イエベ
- 紺色が似合う → ブルべ
茶色は黄みをベースにした暖かい色、紺色は青みをベースにした冷たい色。どちらを着たときに肌の血色やツヤが出て見えるかを比べてください。
③ 生成り(オフホワイト) vs 真っ白
- 生成り色(アイボリー系)が似合う → イエベ
- 白(ホワイト)が似合う → ブルべ
実は「白」だけでも見え方は大きく違います。黄みがかった生成りはイエベに馴染みやすく、真っ白はブルベをシャープに引き立てます。
④ 黄緑 vs 青緑
- 黄緑が似合う → イエベ
- 青緑が似合う → ブルべ
黄緑は春らしい明るい色味でイエベの肌に調和しやすく、青緑は涼しげでブルベに透明感を与えます。
チェックのコツ
ここで注意したいのは「なんとなく似合う気がする」ではなく、具体的に観察することです。
- 顔色がよく見えるか
- 肌色がクリアに見えるか(透明感が出るか)
このあたりを見極めてみてください。「似合う」という表現は、結局のところ「顔色が良く見えるか」を意味しています。
こうした簡易診断で「自分はイエベ寄りかも?ブルベ寄りかも?」と感じられたら、それだけで普段の色選びがぐっとラクになります。
ただし、この方法はあくまで「目安」。方向性をつかんだ上で、「もっと知りたい」と思ったときにプロの診断を受ければ、結果がよりクリアに腑に落ちるはずです。
男がパーソナルカラー診断をやっても意味ある?
結論から言うと、男性がパーソナルカラー診断をやる意味は十分あります。ただし、メリットの大きさでいえば、女性の方がより強く恩恵を受けやすいのも事実です。
男女共通のメリット
ファッションの世界では、男性も女性も同じように服を着ます。だから「似合う色を知ること」によるメリットは、男女で基本的に変わりません。
僕自身、正式なパーソナルカラー診断は受けていませんが、「自分はイエベだろう」と前提を持って服を選んでいます。そのおかげで「この色は肌に合わないからやめておこう」と判断でき、無駄な買い物や後悔がぐっと減りました。
つまり、自分に似合う色の方向性を知っているだけでも、日常の服選びは驚くほど楽になるんです。
女性の方がメリットが大きい理由
ではなぜ「女性の方がメリットが大きい」といえるのか?それは、女性は服に加えてメイクにも色を活かせるからです。
- ファンデーションの色味(黄み寄りか、ピンク寄りか)
- アイシャドウやリップの発色
- チークのトーン
これらが肌のアンダートーンと合っていれば、透明感が増し、顔立ちまで美しく引き立ちます。逆に合わない色を選ぶと、くすみ・疲れ・老け感につながるので、パーソナルカラーの影響は男性以上に大きく出やすいんです。
最近は男性でもメイクをする人が増えてきました。メイクをする男性は女性と同じだけのメリットを得られるといえます。
オンラインのパーソナルカラー診断をするときのポイントと注意点
個人的に「オンラインのパーソナルカラー診断は精度が落ちる可能性が高い」と考えていますが、とはいえ対面で診断してもらう時間を取るのが難しかったりしますよね。実際、最近はオンラインでパーソナルカラー診断を受ける人が急増しています。
中には「オンラインでも精度の高い診断ができる専門家」がいるのも事実です。
最も定番のプラットフォームといえば「ココナラ![]() 」。検索すると驚くほど多くの診断サービスが出てきます。
」。検索すると驚くほど多くの診断サービスが出てきます。
ただ、数が多すぎて「どこで受けたらいいのかわからない」と迷う人も多いんですよね。そこで、オンライン診断を選ぶときに必ずチェックすべきポイントを整理しました。
①資格を持っているか
まず大前提として確認したいのが、診断者がカラー関連の資格を持っているかどうか。
パーソナルカラーの世界には「日本カラーコーディネーター協会」や「日本パーソナルカラー協会」など、信頼できる団体が存在します。必ずしも資格がすべてではありませんが、体系的に学んでいる人と独学の人とでは、診断の精度や説明の説得力に大きな差が出ます。
②実績の豊富さ(年数・件数)
次に見るべきは、実績の数と経験年数。口コミ件数が多い診断士は、それだけ多くの顔タイプや条件を診てきた経験があります。パーソナルカラー診断は理論だけでなく「経験の引き出し」がものを言う世界。
特にオンライン診断は、照明やカメラ環境によって見え方が変わるため、経験の浅い人だと判断を誤るリスクが高まります。だからこそ「実績が多い人=信頼度が高い」と考えられます。
③プロフィールから説得力が読み取れるか
最後のチェックポイントは、プロフィールやサービス説明文を読んで納得感が持てるかどうか。
- 診断の流れが具体的に書かれているか
- 過去のお客様の声や事例が紹介されているか
- 診断結果をどう活かせるのか説明があるか
このあたりがしっかりしていれば、「結果を聞いても納得できそうだな」という信頼感につながります。逆に「なんとなく雰囲気だけで診断します」という人にお願いすると、せっかくお金を払っても後悔することになりかねません。
まとめ|パーソナルカラーは「縛る」ものではなく「武器」になる
パーソナルカラー診断は「意味がない」と言われることもあります。正直僕も、パーソナルカラー診断は必須ではないと思うし、「ファッションは自由に楽しめばいいじゃん」と思います。でも、使い方次第で毎日のファッションやメイクを大きく変える強力なツールになるのも事実です。
大切なのは、診断結果を絶対視することではなく、「自分に調和しやすい色の傾向」を知って上手に活かすこと。そうすれば、「似合わない色を着たいときはどう工夫するか」という応用まで広がり、ファッションがぐっと自由に、楽しくなるんです。
最初にできることは、自宅でセルフ診断をして自分の傾向を知ること。次に、信頼できるプロの診断を受けて確信を持つこと。最後に、その結果を日常のコーディネートやメイクに落とし込んでいくこと。
こうやって一歩ずつ進めるだけで、買い物の失敗は減り、鏡に映る自分に自信が持てるようになります。
近場で診断を受けられる場所がない場合は、オンライン診断を受けるのもアリだと思います。人気のサービスは予約が埋まるのも早いので、気になる方は早めにチェックしておくのがおすすめです。
もちろん最終的に選ぶのはあなたの自由。でも、興味があるなら試す価値は十分あるといえます。